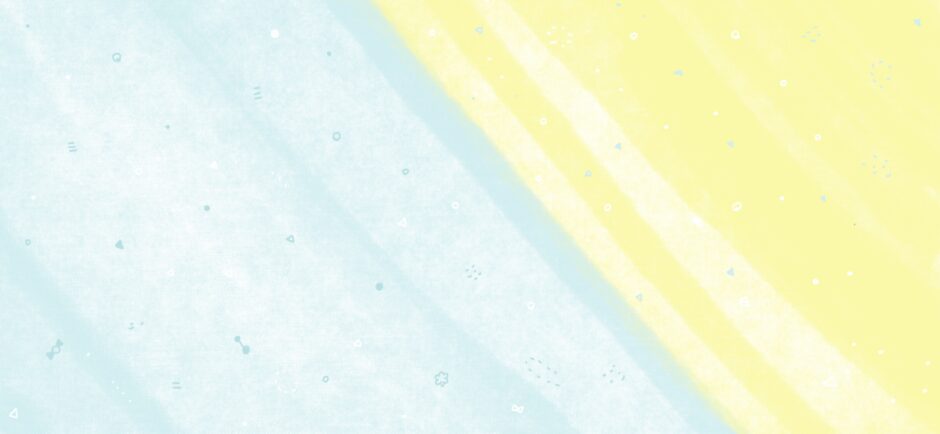布団を干すためにベランダに出て、隣のマンションが視界に入るたびに、一年前のことを思い出して少しだけ口角が上がってしまう。へんてこな邂逅と、その場でへたり込みそうになるほど、ほっとした日の話。
その日は朝から暑かった。空気の入れ替えのために窓を開けると、もわっと湯のような空気に包み込まれたのをよく覚えている。
8時すこし前、窓の外から途切れとぎれに声が聞こえた。泣き疲れた赤ちゃんのような、無条件に助けたくなるような、か細い泣き声。
ベランダに出て、辺りを見回し耳をすましたけれど、それきり聞こえることがなく、網戸の外を気にかけながら、落ち着かない気持ちで朝食を食べた。
おぼろげな声を探しながら、ゴミを捨てに行くと、また声が聞こえる。さっきよりもはっきりと。間違いない、これは猫の声だ。どこかで猫が鳴いている。助けを求めるような鳴き声が、細く長く響いていた。駐車場、エントランス。小走りであちこち見回して、声の出所を探した。分かった、上だ。隣のマンションの上の階から聞こえる。
エレベーターが降りて来る間の、ほんの数秒も待てない気持ちで自宅へ戻り、眼鏡をかけてベランダに出て、隣のマンションを血まなこで注視した。私は視力がさほど良くないけれど、その時はとにかく必死だった。
「にゃーおう……にゃーおう…」不安げな鳴き声は続いている。一階一階、順に焼ききれんばかりの眼光でたどり、ついに見つけた。なんと、マンションの高層階の廊下に猫がいた。うすい灰色のしましまが、廊下を右往左往しているのが見える。なんてこと!飼い主さんが間違えて締め出してしまったんだろうか。
隣のマンションの住居のドアは、我が家のベランダに向き合う形で、歯のようにぴしっと立ち並んでいたけれど、この事態に気がついた様子の住人は見つけられなかった。どうしよう、なんて考えるまでもなかった。そこからの自分の行動は早かった。
水とご飯とちゅーる、それから念のためのキャリーバッグを背負って、すぐに隣のマンションへ駆け出した。初老の優しそうな管理人さんは、血相変えた様子の私にびっくりしていた。
「隣のマンションの者なのですが、こちらの建物の廊下で猫が鳴いているのが見えたんです。◯階です。お願いします、助けてあげてください…!」
呼吸で自分の顔が、鋭く温まるのを感じながらそう言うと、驚きながらも管理人さんは、私とともに猫が居る階に付き添ってくれた。部外者なのに、マンションに入ることを許してくれた。
見つけた階に到着すると、なんと猫の姿はどこにもなかった。見たところ隠れられる場所もない、まっすぐな廊下だというのに。「あれ…?居ませんね…?」どうしよう、どこにも居ない。念のため、上下二階ずつも見させてもらったけれど、猫は見つからなかった。手すりから身を乗り出して、おそるおそる下を見ても、猫の影は見当たらなかった。
70代くらいの管理人さんは「気のせいじゃないですか」とは言わなかった。私の見間違いや、狂言だと疑ったりせず、親身に探してくれた。もうすぐ掃除をする時間なので、そのとき声が聞こえないか気をつけてみますね、と言ってくれた。連絡先を渡すだけ渡して、帰るほかなかった。自分は完全な部外者なので、それ以上留まることは出来なかった。
家に着いても落ち着かない。姿が消えてしまった猫のことが気になって気になって仕方がなかった。仕事をしながらもベランダをちらちら眺め、猫が居ないか何度もサンダルを履き直しては、部屋に戻ることを繰り返していた。細い鳴き声が聞こえた気がしても、姿が見えなかった。
私が家を出て、隣のマンションのエレベーターで上がる間に無事におうちに帰れたのならいいけれど、そうじゃなかったら……。不安でそわそわしながら過ごしていると、夕方になって電話がかかってきた。
「猫、居ました!!!」
はじけるようにキャリーバッグを持って、私は駆け出した。
隣のマンションに到着すると、一階のエントランスで、管理人さんが出迎えてくれた。
「居ました。おっしゃった通りの猫でした。灰色の縞の……」
手でかぼちゃくらいのサイズを示しながらそう言った。
「そうです…!ご連絡ありがとうございます。あの、猫ちゃんはどこに居たんでしょうか」
「えーと。あれは何て言うのかな。見てもらった方が早いですかね…」
2人で話しながらエレベーターに乗り込んだ。例の階には水色の作業服を着たおじさんが居て、廊下の突き当たりの消火栓の下を覗き込んでいた。